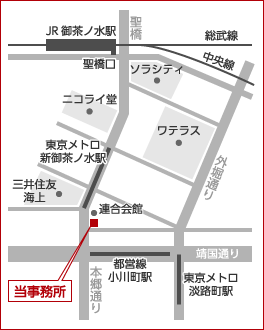最新情報
2019年末から専門委員として消費者庁の自動ドアによる事故の調査に参加しておりましたが、調査報告書が公表されましたのでお知らせします。
調査の端緒となった事故は、前の人に続いて入店しようとした高齢者が、閉まってきた自動ドアの戸先に当たって転倒し、大腿骨骨折の大怪我を負ったというものです。
回転式の自動ドアについては、六本木ヒルズの子どもの死亡事故の後、様々な対策や規制が行われました。
一方、身近にある一般の引戸式については、あまり意識されることはありません。
調べてみると、日常的に大小様々な事故が発生しており、かつ、センサーの設置や感度、反応する範囲などは、個体差が非常に大きいことが分かりました。
つまり、
予想外の動きをする自動ドアが、少なからず存在する、ということになります。
特徴的な例としては、斜め進入によるセンサーの感知遅れや、集合玄関機操作による子どもの挟まれ事故が多く発生しています。
あまりにも対象数が多いため、ドア側での対策を期待するのはなかなか難しい状況です。
まずは、危険があるものとして認識する、子どもや高齢者は皆で見守るということが必要と思われます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2020年12月26日 (土) ~ 2021年1月4日 (月)
上記期間内にいただきました全てのご連絡につきましては、原則、1月5日(火)以降にご連絡させていただきます。
また、2021年も、引き続きリモートワークを併用させていただきます。
ご不便をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2019年8月12日 (水) ~ 8月14日 (金)
土日を合わせた8月12日(水)~16日(日)の期間内の対応につきましては、
新規のご相談、ご依頼中の件ともに、原則として8月17日(月)以降のご連絡とさせていただきます。
期間中のメールでのご連絡は承りますが、急ぎの対応は致しかねます。
また、期間後も、順次のお返事となりますので、多少のお時間がかかる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
国土交通省より、「建設現場「三つの密」の回避等に向けた取組事例」の資料が公表されています。
現場でのリスクと対策が具体的に写真で列挙されており、分かりやすい資料です。
現場の感染対策に、また、発注者や下請への説明資料、打合せにも活用できると思われます。
併せて、関係通知等もまとめられていますので、参考にしてください。
令和2年4月からの民法改正に向けて検討中とされていた、民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の改正ですが、昨年末、その概要が、同約款委員会のHPで公表されました。
約款の頒布開始は3月からだそうです。民法改正後の4月の契約から使用します。
なお、約款の改正に合わせて、「旧四会」から「七会」へと名称変更がなされるようです。
(「七」は「ナナ」なのか「シチ」なのか、気になります。)
約款委員会HPの解説によると、「旧四会」と「七会」とは以下の団体だそうです。
「旧四会」
建築學會(現在の一般社団法人 日本建築学会)
建築業協會(現在の一般社団法人 日本建設業連合会)
日本建築協會(現在の一般社団法人 日本建築協会)
日本建築士會(現在の公益社団法人 日本建築家協会)
「七会」
一般社団法人 日本建築学会
一般社団法人 日本建築協会
公益社団法人 日本建築家協会
一般社団法人 全国建設業協会
一般社団法人 日本建設業連合会
公益社団法人 日本建築士会連合会
一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2019年12月27日 (金) ~ 2020年1月5日 (日)
12月27日にいただきました新規のご連絡(お電話、メール)、上記期間内にいただきました全てのご連絡につきましては、原則、1月6日(月)以降にご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
本日(令和元年12月23日)、令和2年4月に施行される改正民法への対応等のため、中央建設業審議会で建設工事標準請負契約約款の改正が決定され、その実施が勧告されました。
以下、中建審WGで議論されてきた民法改正に関する問題意識について、
11月7日付の記載を残しておきます。
******
■ 契約不適合責任について(約款第44条等)
・担保責任期間のあり方
・代金減額請求権の位置づけ
■ 契約解除について(約款第47条等)
・建物・土地に関する契約解除の制限規定(旧635条)が削除されることに伴う規定の整備
・(解除が制限される不履行の)軽微の範囲について
■ 譲渡制限特約について(約款第5条、第34条、第36条等)
・債権譲渡による資金調達の円滑化という民法改正の趣旨を踏まえた特約条項のあり方
・特約条項違反を理由とする契約解除の取扱い
(民法改正以外では、建設業法改正の反映)
いよいよ約款の改正試案(10月24日資料)が具体的に議論され、とりまとめが近いようです。
上記の2点(瑕疵担保責任→契約不適合責任、解除)については、改正試案でも変更が大きい部分です。
また、個人的には、瑕疵担保と解除の点に目が向きがちでしたが、
譲渡制限特約と資金調達の問題については、日経新聞でも取り上げていました(令和元年11月4日付朝刊)。
改正試案では、相手方の事前の承諾に関する条項(選択式)が追記されています。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款も、年内取りまとめを目処に検討作業中とお聞きしています。
こちらの改正内容を推測する意味でも、中堅審約款に注目しています。
先日、顧客会社様の社内セミナーとして、建築プロジェクトにおける民法改正等のお話をさせていただきました。
聴衆の皆様は、高いレベルの建築プロジェクトをマネジメントされている方々ですので、請負・売買における変更点を中心に、委任(準委任)、時効、経過規定等を、オリジナルの資料と新旧条文対照表を使って説明させていただきました。
具体例を挟みながらお話ししたのですが、少し難しかったとの感想をいただきました。
請負については条文の変化が大きいことや、通常業務では契約書が中心であり、民法まで立ち戻って考える機会は少ないことから、一度きりの説明でご理解いただくのは難しかったかもしれません。
とりあえずは、改正の概要と当面の対応を把握していただき、来年4月以降、必要な場面に直面した場合に、お配りした資料や条文を見返していただければよいかと存じます。
また別の機会があれば、時間を少し長めに取るか、説明のポイントを絞って、契約の基本(請負契約の内容を決するものは何か、等)の復習を併せて行うことも検討したいと思います。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
2019年8月13日 (火) ~ 8月16日 (金)
前後の土日・祝日を合わせた8月10日(土)~18日(日)の期間内の対応につきましては、
新規のご相談、ご依頼中の件ともに、原則として8月19日(月)以降のご連絡とさせていただきます。
期間中のメールでのご連絡は承りますが、急ぎの対応は致しかねます。
また、期間後も、順次のお返事となりますので、多少のお時間がかかる可能性があります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
昨年(平成30年)6月20日に成立した改正建築基準法の施行日が、令和元年6月25日に決定しました。
なお、一部については、既に昨年9月25日に施行されています
・密集市街地等の整備改善に向けた規制の合理化
防火地域や準防火地域における延焼防止性能の高い建築物について、建蔽率を10%緩和するとともに、技術的基準を新たに整備する。
・既存建築物の維持保全による安全性確保に係る見直し
既存不適格建築物に係る指導・助言の仕組みを導入する。また、維持保全計画の作成が必要となる建築物等の範囲を拡大する。
・戸建住宅等を他用途に転用する場合の規制の合理化
耐火建築物等としなければならない3階建の商業施設、宿泊施設、福祉施設等について、200㎡未満の場合は、必要な措置を講じることで耐火建築物等とすることを不要とする。
また、200㎡以下の建築物の他用途への転用は、建築確認手続きを不要とする。
・建築物の用途転用の円滑化に資する制度の創設
既存建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の全体計画認定制度を導入する。また、建築物を一時的に他の用途に転用する場合に一部の規定を緩和する制度を導入する。
・木材利用の推進に向けた規制の合理化
耐火構造等としなくてよい木造建築物の範囲を拡大するとともに、中層建築物において必要な措置を講じることで性能の高い準耐火構造とすることを可能とする。
また、防火・準防火地域内の2m超の門・塀について一定の範囲で木材も利用可能とする。
・用途制限に係る特例許可手続の簡素化
用途制限に係る特例許可の実績の蓄積がある建築物について、用途制限に係る特例許可の手続において建築審査会の同意を不要とする。
※「必要な措置」「一部の規定」等は、関係政令の整備等に関する政令に規定されます。
Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/hjrblaw/hjrb-law.com/public_html/wp-content/themes/pokerface/category.php on line 48
Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/hjrblaw/hjrb-law.com/public_html/wp-content/themes/pokerface/category.php on line 48