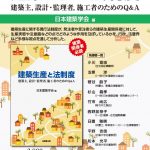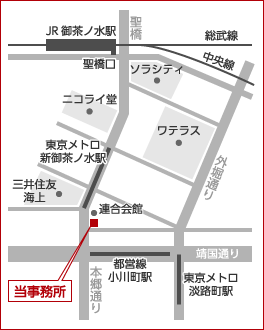最新情報
平成31年3月15日の建築ニュースでお伝えした改正建設業法は、令和元年6月5日、国会で成立しました。
施行は、令和2年末までを予定しています。
****以下、閣議決定時の建築ニュース****
国土交通省は、「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」の閣議決定を発表しました。
国土交通省プレスリリース(平成31年3月15日)
国会の審議・議決を経て、さらに公布の日から1年半以内の施行ですので、少し先の話となります。
技術者配置・経営業務管理責任者の緩和がある一方で、適正発注に関する項目は厳格化されています。
注文者の情報提供義務を定めているのは、非常に興味深いです。
建設業法の改正内容のうち、個人的に重要と考える事項を列挙します。
(法律案要綱から抜粋)
一 許可基準の見直し
建設業の許可基準のうち、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者を置くこととする基準を、建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合することに改めるものとすること。(第7条関係)
三 請負契約における書面の記載事項の追加
建設工事の請負契約における書面の記載事項に、工事を施工しない日又は時間帯の定めに関する事項等を追加するものとすること。(第19条関係)
四 著しく短い工期の禁止
1 注文者は、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないものとすること。(第19条の5関係)
2 国土交通大臣等は、発注者が1に違反した場合において特に必要があると認めるときは、当該発注者に対して勧告することができるものとし、その者が当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができるものとすること。(第19条の6関係)
五 工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供
注文者は、契約を締結するまでに、建設業者に対して、その発生のおそれがあると認めるときは、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象に関する情報を提供しなければならないものとすること。(第20条の2関係)
六 下請代金の支払方法
元請負人は、下請代金のうち労務費に相当する部分については、現金で支払うよう適切な配慮をしなければならないものとすること。(第24条の3関係)
七 不利益な取扱いの禁止
元請負人は、その違反行為について下請負人が国土交通大臣等に通報したことを理由として、当該下請負人に対して、取引の停止その他の不利益な取扱いをしてはならないものとすること。(第24条の5関係)
九 監理技術者の専任義務の緩和
工事現場に監理技術者を専任で置くべき建設工事について、当該監理技術者の職務を補佐する者としてこれに準ずる者を専任で置く場合には、当該監理技術者の専任を要しないものとすること。(第26条関係)
十 主任技術者の配置義務の合理化
特定の専門工事につき、元請負人が工事現場に専任で置く主任技術者が、下請負人が置くべき主任技術者の職務を併せて行うことができることとし、この場合において、当該下請負人は、主任技術者の配置を要しないものとすること。(第26条の3関係)
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2018年12月29日 (土) ~ 2019年1月6日 (日)
上記期間内にいただきましたご連絡につきましては、
お電話(留守番電話への伝言)、メールとも、1月7日(月)以降にご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
1本目は、問題発覚当時において、国交省・製造会社から発表と新聞等の報道を前提とし、当事務所なりの問題意識をコメントしたものです。
2本目は、上記の翌週に、民事責任を改めて検討する必要性や、契約の流れと責任の整理、瑕疵担保責任を問えないケース、等についてコメントしました。
下記の一部について9月25日から施行されること、また、改正法に合わせた施行令の内容が決定されました。
先行して施行される改正
・木造建築物等である特殊建築物の外壁等に関する規制の廃止
・接道規制の適用除外に係る手続の合理化
・接道規制を条例で付加できる建築物の対象の拡大
・容積率規制の合理化(老人ホーム等の共用の廊下等)
・日影規制の適用除外に係る手続の合理化
・仮設興行場等の仮設建築物の設置期間の特例
詳しくは、国土交通省のプレスリリースへ
平成27年から参加しておりました
日本建築学会建築法制委員会
「建築生産関係者と法規範を巡る論点に関する基礎的研究委員会」
の研究成果が、この度、共著として出版されました。
日本建築学会編「建築生産と法制度 建築主、設計・監理者、施工者のためのQ&A」
技報堂出版株式会社(定価2,800円(税別)、178頁)
建築基準法・確認検査の現状について、
また建築生産者(設計者・監理者、施工者等)の責任について、
建築行政に携わってきた方々、研究者、第一線の施工者、まちづくり専門の弁護士など
多彩な顔触れが論じているものです。
また、委員による解説・シンポジウム(研究協議会)が開催されます。
日本建築学会大会
日時:平成30年9月4日(火)13:45~17:15
場所:東北大学川内北キャンパス 川内北講義棟(B棟)B101室
日本建築学会大会にご参加の方、興味がありましたら、是非、ご参加ください。
研究協議会用資料
「建築生産(設計・監理・施工)における建築法制度の現況と今後を考える」
につきましても、現地にて頒布(有償)の予定です。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を夏季休業とさせていただきます。
(昨年はお盆での設定でしたが、本年は諸般の事情により前倒しさせていただきました。)
2018年7月30日 (月) ~ 8月2日 (木)
上記期間内の対応について
・新規のご相談のお申込みにつきましては、8月3日(金)以降にご連絡させていただきます。
・ご相談・ご依頼中の件につきましては、電話での伝言、メール連絡を承ります。
順次、お返事をさせていただきますが、返信まで多少のお時間がかかる見込みです。
また、急ぎの対応は難しくなります。
ご迷惑をおかけしますが、何卒、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
国会で改正建築基準法が成立しました。
本改正は、昨年末からのパブリックコメント、
本年2月の社会資本整備審議会建築分科会・建築基準制度部会からの第三次答申を受けたもので、
・建築物・市街地の安全性の確保
・既存建築ストックの活用
・木造建築物の整備の推進
を柱とするものです。
詳しくは、国土交通省HP 閣議決定のプレスリリースをご覧ください。
東京都より、耐震診断促進法に基づく、耐震診断が義務付けられている建築物の耐震診断結果が公表されました。
新聞報道にもありますが、繁華街の著名な商業ビルのいくつかで、危険性が高い、又はある、との判定結果となっており、かつ、耐震化の目途が立っていない状況です。
一方、「危険性が低い」という判定となった建物も多数あります。割合的には、こちらの方が多数です。
コラムを更新しました。→ 東京都耐震診断結果 コラム
本年(平成30年)、当事務所は以下の3つの点(+番外)に注目しています。
① 建築ストック問題(に対応する基準法改正)
② 民法改正
③ 建設労務環境の変化(建設業法的視点)
番外「IT」の活用 → 平成30年 年頭のコラム
これらの問題についても、積極的に依頼者、業界、そして社会全体のお役に立っていきたいと思いますので、本年も宜しくお願い致します。
日頃より当事務所をご愛顧いただき、どうもありがとうございます。
誠に勝手ながら、当事務所は、以下の期間を年末年始のお休みとさせていただきます。
2017年12月29日 (金) ~ 2018年1月4日 (木)
上記期間内にいただきましたご連絡につきましては、
お電話(留守番電話への伝言)、メールとも、1月5日(金)以降にご連絡させていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/hjrblaw/hjrb-law.com/public_html/wp-content/themes/pokerface/category.php on line 48
Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/hjrblaw/hjrb-law.com/public_html/wp-content/themes/pokerface/category.php on line 48